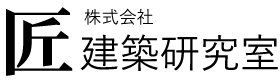オリジナル・オーダーメイドの空間
 現代では建築を取り巻く環境がめざましく変化し、そこを使う人々のニーズも多様化しています。 現代では建築を取り巻く環境がめざましく変化し、そこを使う人々のニーズも多様化しています。匠建築研究室では、戸建住宅はもちろん、マンションやアパート、店舗、オフィス、公共施設などさまざまな建築の設計を行っています。私たちは、建主とのコミュニケーションを大切にし、お客様にとって本当に必要なものを発見し専門知識を駆使して、敷地条件、機能、コスト、環境などの問題も解決し、質の高いデザインによるオリジナルな空間を提供します。
では、なぜ「オリジナル・オーダーメード」が必要なのでしょうか。顔や性格が一人一人違うように、生活スタイルも違えば求める理想の住宅も様々です。そして、住宅を建てようとする敷地は世界に1つしかありません。敷地が違えば、その形状、規模、入口の方向、周辺環境などが違ってきます。周辺環境に関係なく建物を建てられるような広大な敷地を持っていれば別ですが、普通はすぐ隣の家が接しているような100坪未満の敷地がほとんどだと思います。私たちはまず、その大事な土地を最大限に有効利用するにはどうするか、というところから考えます。その土地の悪条件を克服し、良い条件を引き出したいと思います。日照、通風、騒音、景観などを検討し、その敷地の持っているポテンシャルを引き出していきます。 |
設計事務所の仕事について
あなたが家を建てようと思ったとき、まず何をするでしょうか? とりあえず雑誌やインターネットを見る。ハウスメーカーの住宅展示場に行く。最近家を建てた知人に相談するなどでしょう。いずれにしても、情報を集める事が必要で、どのような家をつくりたいか、少しでもイメージを膨らませる事が大切です。
とりあえず雑誌やインターネットを見る。ハウスメーカーの住宅展示場に行く。最近家を建てた知人に相談するなどでしょう。いずれにしても、情報を集める事が必要で、どのような家をつくりたいか、少しでもイメージを膨らませる事が大切です。
しかし、最初から設計事務所に頼もうと考える方は、設計事務所に知人がいるという方でもない限り、まずいないと思われます。その理由としては、「どこの設計事務所に頼んで良いか判らない」、「設計事務所に頼むと高そう」、「なにか奇抜なものをつくられそう」………などではないでしょうか。
最近では、インターネットにより情報発信したり、雑誌などでデザイナーズハウス(マンション)が紹介されたり、テレビでリフォーム番組などが放送されたりして建築家、建築士などの仕事が目に触れるようになってはきました。しかし、設計事務所がいまだに一般的ではないのは、まだ設計事務所の敷居が高いのかもしれませんし、自分たちの活動を広く社会にアピールしていない私たち自身の責任でもあります。
ここでは、私たち設計事務所の仕事の内容を紹介しながら、建物が出来るまでを御説明いたします。
【建築士、建築士事務所とは・・・】
匠建築研究室は一級建築士事務所として、複数の一・二級建築士で構成しています。
建築士事務所とは、建築の設計、工事監理、建築工事の指導監督、建築 工事契約に関する事務等を行う建築設計事務所のことで建築士法に基づいて都道府県知事の登録をしているものをいいます。そして、国家試験により、国土交通大臣より免許を受けた一級建築士、都道府県知事の免許を受けた二級建築士、木造建築士などの資格者がその業務を行っています。
工事契約に関する事務等を行う建築設計事務所のことで建築士法に基づいて都道府県知事の登録をしているものをいいます。そして、国家試験により、国土交通大臣より免許を受けた一級建築士、都道府県知事の免許を受けた二級建築士、木造建築士などの資格者がその業務を行っています。
一級建築士はその業務に制限はありませんが、二級建築士・木造建築士は、面積や用途、構造などにより設計、工事監理の出来る範囲に制限があります。専用住宅に関しては、高さが13mをこえるもの、軒の高さが9mをこえるもの、木造以外で延べ面積が300㎡をこえるものは一級建築士でなければ出来ません。
【設計事務所の仕事とは・・・】
大きく分けて、設計事務所の仕事は、設計と工事監理に分かれます。
設計とは、建築物の工事を実施するために必要な図面及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成する事です。法律的なチェックをし、確認申請業務も行います。
設計に入る前にはあらかじめ敷地調査、地盤調査、近隣の調査、検討などを行います。そして、建主との綿密な打合せを随時行いながら、その意図・企画・要望・御予算等を十分理解した上で、具体的な形にしていきます。ここまでを基本設計と言います。この基本設計に基づいて、工事施工業者が工事を実施する為に必要な詳細な図面を作成します。これを実施設計と呼んでいます。実施設計では、構造設計、電気設備設計、機械(給排水・ 空調)設備設計の担当者も交えて、その作成にあたります。
空調)設備設計の担当者も交えて、その作成にあたります。
工事監理とは、建物に応じた施工会社を選定し、見積を依頼したりその見積の内容を検討し、建主に報告します。そして、工事に先立ち、建主と施工者が適正な工事請負契約を結ぶ事が出来るよう協力します。
いよいよ工事が始まれば、施工者に設計意図を正しく実現させる為に指示を行ったり、設計図書のとおりに実施されているかを確認します。使う材料やその色などを選定し、最終的に建主に決定していただくための作業も行います。工事完成にあたっては、役所の完了検査を受け、竣工検査を行います。そして、いよいよ引渡しとなります。
これで、一応、業務の完了となりますが、引き渡し後もアフターケアや、瑕疵検査の実施(通常は1年後)に立会います。
これまでの説明をフローチャートにすると次のようになります。
設計監理業務の流れ
ここでは、ご相談から設計、着工、現場監理、竣工、引渡しまでの簡単な流れを説明します。
| 御希望、御予算、敷地の状況などをお聞きした上で、プランの方針などを検討します。(無料) | |
| ・敷地条件の整理 ・関係法規の調査 ・イメージの調整(規模、予算含む) | |
| ・可能性の検討 ・イメージの具体化 ・規模、構造、予算等の検討 | |
| ・規模、構造、予算等の具体化 | |
| ・平面図、立面図、仕上図等の作成 | |
| ・詳細図の作成、設備図の作成 ・確認申請の提出 | |
| ・工事業者の決定 | |
| ・監理業務 ・仕上、色等の最終決定 | |
| ・完了検査 ・引渡し | |
【設計事務所に頼むメリットとは・・・】
設計事務所の仕事の概要については、だいたいおわかりになっていただけたでしょうか。それでは、設計事務所に設計を頼むと、どんなメリットがあるのでしょうか。
1.建主の立場に立った設計・監理が出来る
 設計事務所に仕事を依頼し、建築士とつくる家の最大のメリットは、「建主の立場に立った設計・監理が出来る」ということにあります。家を造ることは、多くのお金はもちろん、時間や労力を伴います。設計事務所の設計者は、その作業を建主と一緒に二人三脚で共同作業を行うプロのパートナーといえる存在です。
設計事務所に仕事を依頼し、建築士とつくる家の最大のメリットは、「建主の立場に立った設計・監理が出来る」ということにあります。家を造ることは、多くのお金はもちろん、時間や労力を伴います。設計事務所の設計者は、その作業を建主と一緒に二人三脚で共同作業を行うプロのパートナーといえる存在です。
そして、専門的な能力を生かし、建主の利益を守っていきます。
もちろん、ハウスメーカーにも一級建築士がおり、工事監理のプロもいます。また、メーカーによっては、設計事務所に設計を外注する事もあります。しかし、それらの設計者と私たちは立場が違います。それは、誰から報酬をもらって働いているかという点です。それらの設計者は、依頼者(ハウスメーカー)の利益を最優先にするのは当然の事です。
2.オリジナルな個性あふれる家が出来る
 「オリジナル、オーダーメイドの空間」で述べたように、建築とは本来、オリジナルで、オーダーメードのはずです。もちろん、ハウスメーカーの家を否定するわけではありませんし、多くの方がハウスメーカーの家を選んでいる事は事実です。しかし、「フリープラン」や「自由設計」などのうたい文句で、建主の自由に造れますと説明しますが、実際は、構造、仕上、デザインなどでかなり制約があり、規格を外れると値段がだんだん高くなるのが一般的です。
「オリジナル、オーダーメイドの空間」で述べたように、建築とは本来、オリジナルで、オーダーメードのはずです。もちろん、ハウスメーカーの家を否定するわけではありませんし、多くの方がハウスメーカーの家を選んでいる事は事実です。しかし、「フリープラン」や「自由設計」などのうたい文句で、建主の自由に造れますと説明しますが、実際は、構造、仕上、デザインなどでかなり制約があり、規格を外れると値段がだんだん高くなるのが一般的です。
本当の意味での自分だけのオリジナルな家を御希望なら、設計事務所に依頼することをお勧めします。
3.予算を有効に活用できる
大抵の方は、限られた予算の中で、良い家をつくりたいはずです。しかし、限られた予算の中で、全ての要望をかなえる事が不可能な場合、設計事務所では建主の要望から優先順位を整理し、無駄を省いたコスト配分をします。
たとえば、外壁の仕上のグレードを落としても、リビングだけは仕上に本物の木材を使う。寝室は必要最小限のスペースにして、LDを広くし床暖房にする。このように、建主にとって何が一番大切かという事を建主の立場に立って提案していきます。
また、設計事務所に頼むと設計料が余分に掛かると思っていませんか。設計料は何処に頼んでも、経費として取られたり、工事費の中に含まれていたりします。
工事費についても、設計事務所では設計図が出来てから、複数の業者に見積合わせを依頼し、さらに、各社から出てきた見積書を細かくチェックしますので、競争の原理が働き、結果として、安くて良いものが出来ます。また、設計図に基づいて、適切な工事監理を行う事で、手抜き工事を防止し、建主の利益を守ります。(手抜き工事により、せっかくつくった財産が台無しになってしまっている事例があることは、テレビなどで御存知だと思います。)
コストについても、初期投資となるイニシャルコスト(いわゆる工事費)とランニングコスト(生活が始まってからの光熱費、建物の維持補修費など)についても検討します。たとえば、ある設備機器などは、イニシャルコストは高いが、光熱費が安いのため何年で回収できるので採用した方が良い、というような検討です。
設計事務所では、これらのことによりトータルでコストを安く出来、設計料に相当する価格以上の効果を期待できます。
【設計事務所に頼まないほうが良いと思われる方】
家を造るなら設計事務所に頼んだほうが良いと言ってきましたが、逆に、頼まないほうが良いと思われる場合もあります。
1.特に自分らしい家をお望みでなく、他の家と同じような家をお望みの方
特に、自分のライフスタイルにあったオリジナルな家をお望みでなく、他の家と同じような家を手に入れたいと思っている方はハウスメーカーをお勧めします。
現在新築されている日本の住宅のほとんどがハウスメーカーのものであり、これが一般的だからです。
2.できるだけ手間をかけないで家をつくりたい方
家をつくるという事は、お金だけでなく時間と労力が掛かります。車を買う事と同じような感覚で家を手に入れたいと思っている方は設計事務所に頼まないほうが良いでしょう。良い設計をするには最低でも3ヶ月以上必要ですし、何度も打合せをお願いする必要があるからです。
3.自分さえ良ければ良い、他人の意見に耳を傾けるのが嫌な方
建築物とは、個人の所有物であっても社会性があり、周辺環境に配慮したものでなければならないと考えます。よって、周辺環境に悪影響を及ぼすものや、経済性だけを優先した粗悪なものは建主の希望でも設計することは出来ませんので、依頼されてもお断りするようになります。もちろん、法律に抵触するような建物の設計も行いません。
設計をするにあたっては、当事務所と建主は信頼関係で結ばれていなければならないと考えます。私たちは、皆さんの意見に一生懸命耳を傾けます。皆さんも私たちの意見を、プロとして総合的に判断したものとしてお受け取り下さい。私たちと家造りのパートナーとしてその存在を認めていただけることが必要だと思います。
家をつくりたい
 これまで私たちのホームページを読んでいただき、少しでも設計事務所に設計を頼んで家をつくってみようと思っていただけたでしょうか。ここではそのような方に家をつくるためのワンポイントアドバイスをしたいと思います。
これまで私たちのホームページを読んでいただき、少しでも設計事務所に設計を頼んで家をつくってみようと思っていただけたでしょうか。ここではそのような方に家をつくるためのワンポイントアドバイスをしたいと思います。
【敷 地】
良い建築とは、その敷地に違和感無く納まっている事が必要だと思います。別な言い方をすると、その敷地にしか合わないような建築なのかもしれません。
まず、大切な建主の敷地をどうやって有効に利用するかを考えます。敷地条件は、様々であり、敷地が狭かったり不整形だったとしても心配ありません。それでも、良い環境を創出することが私たちの仕事です。
【構 造】
建物の構造としては一般的な住宅程度の規模であれば、次のようなものがあり、御要望、予算に応じた設計が出来ます。
| ●木造 一般的な住宅に多く用いられる構造です。木造の中でも軸組工法(いわるゆ在来工法)、枠組壁工法(2×4工法、2×6工法など)などがあります。施工がしやすく、工期も他の構造に比べ、短くて済みます。高級な木材(銘木)を使わなければ他の構造と比べて工事費を抑えられます。しかし、大きな空間を造る場合には向いていませんし、形にも制限があります。
●鉄筋コンクリート造
●鉄骨造
●その他 |
 【プランニング】
【プランニング】
プランニングについては家それぞれ違いますが、まず皆さんは最初にどのような部屋が欲しいか考えると思います。
リビング、ダイニングは当然広く、システムキッチンを入れて台所も広く、和室も必要で出来れば二つ、広い縁側をつけて、玄関も広く、ピアノを置くスペースも欲しい、広い寝室にウォークインローゼットを付けて、サンルーム……
あっという間に敷地からはみ出してしまいそうです。
アドバイスとしては、まずは、今の生活をベースに考えてください。今、タタミで寝転んでテレビを見てくつろいでいるのが好きなあなたが、急にリビングの大きなソファーでブランデーグラスを傾けるなんてありえません。本当に自分のライフスタイルに合った空間(部屋ではなくて)には何が必要なのかを考えてみてください。
<部屋ではなくて空間から考えてみる>
 どのような家をつくりたいかを聞かれれば大抵の方は、リビング、ダイニング、キッチン、寝室、子供部屋……と部屋の名前を列記すると思います。そこにはリビング=くつろぐ、ダイニング=食事をする、寝室=寝る、といった機能を無意識に当てはめているはずです。そして、ソファー、ダイニングテーブルなど置く家具までイメージされているはずです。なぜその部屋が必要なのですかと聞かれれば、なんとなく、普通あるからといった答えが返ってきます。ハウスメーカーのモデルプランなどはそのように構成したほうが判り易すく、イメージをつかみ易いと思いますが、実際の生活は違います。食事をする場面を考えても、家族全員で朝食を取る、1人でデレビを見ながら食べる、休みの日にビールを飲みながらテラスで昼食を取る、友人を呼んで大勢で食べる、料理を一緒に作りながら夫婦だけで食べる、深夜に一人で軽く飲みながらつまむ、……など上げたら切りがありません。発想をちょっと変えただけで、家中すべて(さすがにトイレは無理ですが)、外部までも食事をするスペースになります。
どのような家をつくりたいかを聞かれれば大抵の方は、リビング、ダイニング、キッチン、寝室、子供部屋……と部屋の名前を列記すると思います。そこにはリビング=くつろぐ、ダイニング=食事をする、寝室=寝る、といった機能を無意識に当てはめているはずです。そして、ソファー、ダイニングテーブルなど置く家具までイメージされているはずです。なぜその部屋が必要なのですかと聞かれれば、なんとなく、普通あるからといった答えが返ってきます。ハウスメーカーのモデルプランなどはそのように構成したほうが判り易すく、イメージをつかみ易いと思いますが、実際の生活は違います。食事をする場面を考えても、家族全員で朝食を取る、1人でデレビを見ながら食べる、休みの日にビールを飲みながらテラスで昼食を取る、友人を呼んで大勢で食べる、料理を一緒に作りながら夫婦だけで食べる、深夜に一人で軽く飲みながらつまむ、……など上げたら切りがありません。発想をちょっと変えただけで、家中すべて(さすがにトイレは無理ですが)、外部までも食事をするスペースになります。
皆さんも、リビングや客間といった部屋名ではなく、広いフローリングのスペース、落ち着いた畳のスペース、庭の見えるカウンター、みんなの顔が見えるキッチンなどイメージを空間に当てはめて家のプランを考えてみませんか。今までとちがったあなただけの家が見えてくるはずです。
雑誌やテレビドラマ、モデルハウスなどを見ていると、「ステキな空間」が目に飛び込んできます。「絶対にこのようにしたい」と夢が膨らむ事でしょう。でも、冷静になって本当に自分にとって必要なのか、考えてください。注意しないと、せっかく造っても次のように、結局使われない事になります。
テレビなどでは良く見かけるが、造っても結局使われないものをあげると、
(当然、匠建築研究室で家を建てられた方はこんな事はありません。念のため)
| ●キッチンに面してちょっと食事が出来るカウンターが欲しい ⇒すぐ隣にダイニングテーブルがあるのにわざわざカウンターで食事をすることはないと思います。今はやりのアイランドキッチンは、家でほとんど料理はしない方にはお薦めしますが、普通に料理を作ろうと思う方は止めたほうが良いでしょう。常に綺麗に片づけておくのは大変です。 ●お客が来た時に見栄えがするような、大きな床の間が欲しい ●パソコンスペースが欲しい ●ロフトを設けて、ホビースペースにしたい |
※このほかにも、いろいろあると思いますので、みなさんも誰かの家で見かけたら御一報下さい。参考になるものはここに掲載させて頂きます。
【長持ちする家】
 建物の寿命を考えると、いわゆるハード面の「耐久性」とソフト面の「使い勝手」の二つについて考える事が必要です。
建物の寿命を考えると、いわゆるハード面の「耐久性」とソフト面の「使い勝手」の二つについて考える事が必要です。
「耐久性」については、耐震性能や構造体、仕上材、設備機器の性能です。これについては、普通に信頼できる設計と施工、常識的なコストによる建物であれば特に問題は無いはずです。匠建築研究室では手抜き工事などを見逃さない確かな設計者の目であなたの財産を守ります。また、耐久性で重要な事は、その後のメンテナンスです。メンテナンスが要らない建物はありません。きちんとした使い方と、適切な時期に、きちんとしたメンテナンスをすれば建物の寿命は長くなります。
もう一つの「使い勝手」ですが、どの程度まで将来を見据えるかは大変難しい問題です。将来の家族構成や、ライフスタイル、健康状態がどうなるかなど、把握できるものではありません。出来るだけ将来を見据えながら、将来のリフォーム、リニューアルなどに配慮していく事が重要だと想います。

私たちの事務所は、多くの公共建築を手がけています。このノウハウを活かし、「耐久性」があり、「使い勝手」の良い、「バリアフリー」などに配慮した家づくりを行います。
<家族構成もライフスタイルも変化していく>
子供が出来る、親と同居する、子供が独立するなど家族の構成やそのライフスタイルは変化していきます。難しい問題ではありますが、そのような変化に柔軟に対応できることが大切だと思います。
例えば、本当に独立した子供部屋が必要なのは小学校高学年から高校生ぐらいまでの、ほんのわずかな期間だけかもしれません。せっかく立派な子供部屋をつくっても、結局、日の当らないフローリングの寝室で布団を敷いて家族全員で川の字になって寝ていたりなんて事も起こります。
家を建てたらもう終わりなどと考えないで、家族に合わせて家も成長させる事が必要です。といっても、いちいち改修するということではありません。柔軟な発想で、スペースを有効に活用すれば良いのです。子供が小さいうちは和室で全員で寝たり、最初は大きなオープンスペースにしておいて、将来子供が大きくなったら間仕切りを付けたりすれば簡単に出来ます。これも、前に述べたように、部屋の名前で考えないでスペースをイメージする事が大切です。
<バリアフリー>
 バリアフリーやユニバーサルデザインといった言葉は皆さんも良く耳にする事でしょう。これらは体に障害などを持っても通常の生活を送ったり、健常者と障害者が共に生活をしていくといった考えです。家を新築するときは「バリアフリー」でと誰もが考えると思いますが、「バリアフリー」といってもその内容は様々です。障害の内容は千差万別であり、その障害に合った適切な処置をしないと、かえって不便になってしまいます。たとえば、トイレの手摺についても右半身が不自由な人に、右側だけについた手摺は「バリアフリー」どころか障害となります。
バリアフリーやユニバーサルデザインといった言葉は皆さんも良く耳にする事でしょう。これらは体に障害などを持っても通常の生活を送ったり、健常者と障害者が共に生活をしていくといった考えです。家を新築するときは「バリアフリー」でと誰もが考えると思いますが、「バリアフリー」といってもその内容は様々です。障害の内容は千差万別であり、その障害に合った適切な処置をしないと、かえって不便になってしまいます。たとえば、トイレの手摺についても右半身が不自由な人に、右側だけについた手摺は「バリアフリー」どころか障害となります。
まず、家を造るときに家族全員が健康ならば、段差の解消、健常者にとっても便利な手摺の設置、ゆとりある水廻りスペースの確保、トイレを寝室に隣接させる、などを行っておいて、あとは障害を負ったときにそれに合わせて、適切にリフォ-ム出来るようにしておく事が大切だと思います。
<エコロジー>
 建築におけるエコロジーに関しては二つの側面があります。一つ目は地球環境の問題を改善するために私たちが取り組まなければならないこと。自然エネルギーを上手に活かし、環境負荷の低減を行ったり、リサイクル品などを積極的に使い資源を大切にする事です。二つ目は、自然が与えてくれる恵みを五感で感じる事が出来るような、「豊かさ」、「快適さ」、「健康」を追求すること。皆さんもシックハウス症候群という言葉を御存知だと思いますが、塗料や建材などに含まれている化学物質が健康に及ぼす影響が問題になっています。匠建築研究室では、学校や保育園、公営住宅を数多く手がけており、有害物質を含まない材料を使うのはもちろんのこと、完成後に有害物質の濃度の測定を行うなどしています。しかし、建材以外にも花粉、ハウスダクト、カビ、殺虫材、持ちこんだ家具、衣類など科学物質の発生源は多岐にわたります。大切なのは、風通しを良くする、庇を付ける、適切に断熱をする、ペアガラスを使う、よく掃除をするなどで、十分対応できると思います(但し、アレルギーには個人差があります)。つまり、住んでいる人が快適で気持ちの良いことが大切です。
建築におけるエコロジーに関しては二つの側面があります。一つ目は地球環境の問題を改善するために私たちが取り組まなければならないこと。自然エネルギーを上手に活かし、環境負荷の低減を行ったり、リサイクル品などを積極的に使い資源を大切にする事です。二つ目は、自然が与えてくれる恵みを五感で感じる事が出来るような、「豊かさ」、「快適さ」、「健康」を追求すること。皆さんもシックハウス症候群という言葉を御存知だと思いますが、塗料や建材などに含まれている化学物質が健康に及ぼす影響が問題になっています。匠建築研究室では、学校や保育園、公営住宅を数多く手がけており、有害物質を含まない材料を使うのはもちろんのこと、完成後に有害物質の濃度の測定を行うなどしています。しかし、建材以外にも花粉、ハウスダクト、カビ、殺虫材、持ちこんだ家具、衣類など科学物質の発生源は多岐にわたります。大切なのは、風通しを良くする、庇を付ける、適切に断熱をする、ペアガラスを使う、よく掃除をするなどで、十分対応できると思います(但し、アレルギーには個人差があります)。つまり、住んでいる人が快適で気持ちの良いことが大切です。
設計を依頼する方法
ここでは、設計を依頼するにはどのようにすれば良いのかを、私たちの事務所の場合を、住宅を例にとってご説明します。
【準 備】
まずは、自分なりの住宅のイメージを持つ事が必要になります。そのためには、雑誌などの情報を集めたり、家族で夢を語り合ったりする事が大切です。そのときに、このホームページで前述したように、部屋名ではなく空間のイメージで考えてみて下さい。そのイメージは家族一人一人違うはずですから、楽しんで夢を語り合ってください。
それから、予算や規模、建築の時期などの基本的な要望事項を整理して下さい。しかし、この段階ではあまり難しく考えないで、漠然としたものでも大丈夫です。
【相 談】
設計事務所に連絡したら、必ず設計を頼まなくてはならないとか、相談するとお金が掛かるという事はありません。まずは気軽に御連絡下さい。電話やFAX、メールなど何でも結構です。会う事になれば、日時・場所などを決めます。最初にお会いする場所は、当事務所か、敷地調査も兼ねてそちらのお宅にお伺いする場合もあります。
【打ち合せ】
 まず最初にお会いしたら、どのような家を建てたいかなど、なんでも結構ですのでお話下さい。私たちも設計の考えやこれまでの出来あがった建物などをご紹介しながら、お客様の抱いているイメージを掴んでいきます。
まず最初にお会いしたら、どのような家を建てたいかなど、なんでも結構ですのでお話下さい。私たちも設計の考えやこれまでの出来あがった建物などをご紹介しながら、お客様の抱いているイメージを掴んでいきます。
最初はお互いの事を良く知る事が大事だと思います。(お見合いのようなものと考えても良いかもしれません)。
ここで、お互い納得したうえで次の段階に進みます。大抵は敷地調査を行い、与条件などを整理したうえでモデルプランを作成します。モデルプランとは、敷地にどの程度のものが建つか、どのような考え方があるかなど可能性を探ったり、お客様のイメージを具体化するための簡単な平面やイメージスケッチのようなものです。このモデルプランをもとに、何度か打ち合せを行い、お互い理想とする家のイメージを膨らませていきます。もちろん最初のイメージとは違うものに変化していく事もあるでしょうし、敷地条件や法規的な制約が出てくるかもしれません。
【設計の契約】
モデルプランの打ち合せ(通常は2~3回程度)を行い、大体の方針が決まれば、大まかな予算と共に設計料の見積書を提出します。
これらの資料をもとに、設計を依頼するかどうかを御判断下さい。設計料については規模、予算、構造、内容などで違ってきますので、その都度算出しています。一般的には、鉄骨造、RC造のように構造計算が必要な場合は設計料も高くなりますが、御相談に応じて柔軟に対応しています。
もしこの段階で、納得がいかないようであれば、はっきりと断って頂いて結構です。このあたりまでの作業であれば私たちの事務所では無料で行っていますので、御心配はいりません。
設計を依頼したいということであれば、正式な契約書を用意しますので、設計監理の契約を取り交わします。設計料については、通常、①契約時、②実施設計完了時、③監理業務完了時、の3回に分けてお支払頂いています。
【契約後について】
 契約を取り交わした後の事については、【設計事務所の仕事について】、【設計監理業務の流れ】の欄に詳しく載せているのでそちらをご覧下さい。
契約を取り交わした後の事については、【設計事務所の仕事について】、【設計監理業務の流れ】の欄に詳しく載せているのでそちらをご覧下さい。
モデルプランで方針が決まったといっても、そのまま図面を書いて家が出来上がるという事ではありません。ここからが設計の始まりです。デザイン、構造、予算、設備などの詳細を詰めながら、良い空間を具現化する為に検討や打ち合せを重ねます。もっと違うアイデアが出てきて、モデルプランとは違うものになる事もあります。家をつくる作業は、建主と設計者のコラボレーションです。お互い良いアイデアを出しながら、素適な家を匠建築研究室と一緒につくってみませんか。